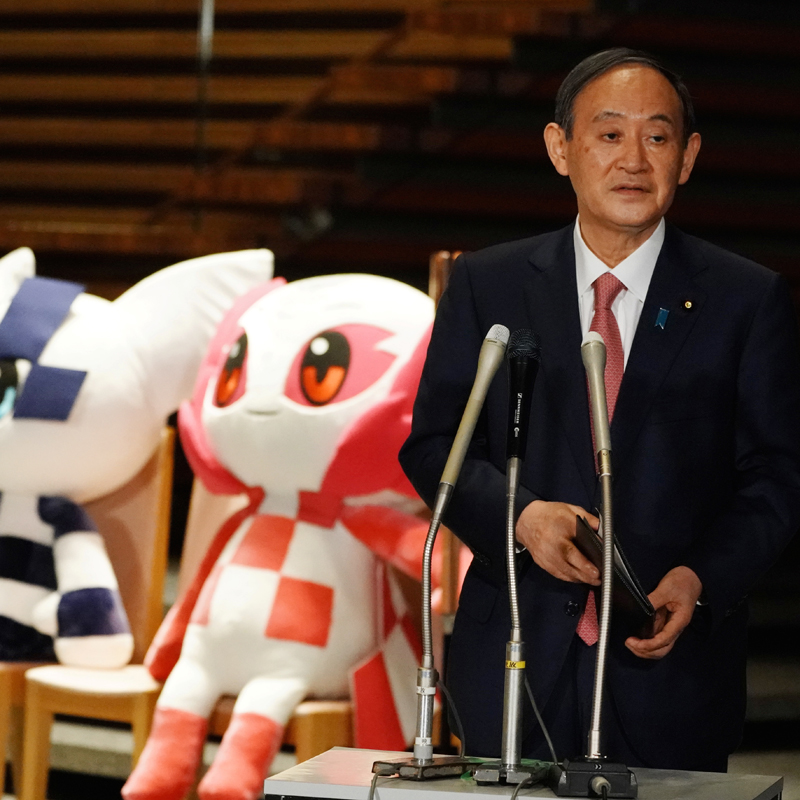「直観」でものごとを判断するということ【中野剛志×適菜収】
中野剛志×適菜収 〈続〉特別対談第3回
適菜:理屈より「直観」のほうが信用できるという話ですね。小林も内面は顔に表れると言いました。「直観」には言語という形で表面に出てこない切り落とされたものが多く含まれている。その点、子供は正直です。王様が裸だったら、「王様は裸だ」と言っちゃうわけですから。「裸だ」という言葉を与えるのは結構大事なことです。ここの部分だけ匿名にしておきますが、某国立大学の大学院教授について、新型コロナで完全におかしくなったとFacebookで指摘したんです。そうしたら、しばらくやりとりのなかった昔の知り合いとかが大勢出てきて、「私も同じことを感じていました。でも、有名な大学の先生なのだから、そんなにおかしなことを言うはずがないと思い込んでいました」と。ツンツンとつつけば、いろいろ出てくるわけです。ある人からは「適菜さんは、人は顔で判断すべきだと言っていたのに、なんであんな顔の人とつるんでいたんですか?」と言われてしまいました。
中野:これは、一本とられましたね。まさに顔で判断するからFacebookなんですか(笑)。偽物と付き合ってしまった自分を反省して言えば、「俺は、大衆と同じ行動を取っていたな」と思います。ここで言う「大衆」という意味は、キェルケゴールが言った意味での「大衆」なんです。要するに、自分が内心つまらないと思っているものを褒めてみせるような連中が「大衆」だということです。私は、内心つまらないと思っていたのに、それを隠して付き合っていました。だから、「大衆」だったんですよ。やっぱり、自分の直観をごまかして、うわべをとりつくろったような社交はいけないんだなと後悔しました。本当に失敗したなっていうか。でも、そんなことばかり言っていると、本当に孤立してしまうな。第1回目の対談で話題になった福沢諭吉の「私立」「痩我慢」っていうことかもしれませんが。
適菜:それこそ、キェルケゴールですね。独りぼっち、単独者になってしまう。キェルケゴールは市民の本質を「第三者」「傍観者」と規定しました。こうした社会では本当のことが、大量の「おしゃべり」の中に埋もれていく。

■「信じることと知ること」
中野:話を戻すと、直観は、本当は、根拠のないものじゃないんですよ。世間では、明示的な知識や理論あるいはデータはちゃんとしたもので、直観はいい加減な思いつきで根拠がないものと思われている。でも、それは全然違う。直観には、暗黙知という明示的ではないけれどちゃんとした根拠があって、ただ、それが明示化されていないので「直観」という言葉になるだけなんです。小林秀雄はまさにこのことを重視していた。
小林の場合はベルグソンの影響だと思いますけれども、例えば、死んだおっかさんがホタルになって飛んでいるのを見たとか、そういう経験を信じることが大事だと書いています。科学が一蹴するような現象についても、まずいったんは信じる。小林の講演のタイトルの「信じることと知ること」ですね。何かを知る前に、まず何かを信じていないといけない。つまり、自分では全部理解していないし、うまく言えないんだけど、なんか正しいと直観することが、信じるということです。うまく根拠を言えないのに、なぜ信じられるのか? オカルトを信じているような異常者は別として、まともな人間が「信じる」というときの感覚は、多分、暗黙知のことなんでしょうね。
適菜:まさにそのことをポランニーが言っているんですよね。《伝統主義とは認識する前に、さらに言えば、認識できるようになるために、まずは信じなければならぬと説くものだ。するとどうやら伝統主義は、知識の本質や知識の伝達に対して科学的合理主義などよりも深い洞察を携えているらしい》(同前)。ポランニーがバークに言及しながら、節度ある自由、聖なるものに対する配慮を説いたのも、知が社会的権威と信任に基づいているからですね。だから、保守的であることや伝統を重んじることは、思想的哲学的にもっとも誠実な態度なのだとポランニーは言ったんですね。左翼の発想はここが180度転倒しているんです。理性や合理によって、すべて判断できると思っているわけですから。
中野:そうなんです。だから知識に到達する前に、「前・知識」として「信じること」がある。先ほど話題に出したコールリッジなんかは、科学の根底には宗教があるとまで言っている。まずは信じることから始める。とりあえず信じることで現実世界や経験に深くコミットする。そうすることで、暗黙の裡に知識を体得する。「acquire」という言葉をポランニーは使っていたと思いますけれど、まさに「体得」ですね。私の理解では、暗黙知を頭ではなく体に取り込んで貯め込んでいくようなイメージです。体得したあとで、その中から頭で処理して明示的な知識や理論を出していく。これが、「分かる」ということなのでしょう。
ただし、人間は、暗黙知の一部しか理論知としてくみ出せない。言葉が表現できるものには限界があるから、明示的な知識や理論として表せるのは、暗黙知のごく一部に限られるのです。一方で、体のほうは、どんどん先に動いて暗黙知を取り込み、積んでいく。だから、人間は行為をし、行動をしないと、現実に密着した暗黙知を体得できず、したがって理論のほうも出てこない。逆にいうと、現実世界の中で行動や実践をしないで理論だけをいじくり回していると、現実から離れていく。なぜならば、現実と理論とをつないでいるのは、体で体得した暗黙知だからです。
適菜:泳げない人が水泳の理論を書くようなものですね。それでも言葉は恐ろしいもので、実際には理論を書けてしまうのですが。小林は、《人類という完成された種は、その生物学的な構造の上で、言ってみれば、肝臓という器官をどうしようもなく持っているように、宗教という器官を持っている》と言っています。そして長年にわたり、宗教とは教理ではなく、祭儀という行動であったと。これは今、中野さんがおっしゃった話と同じです。合理的に考えれば非合理の部分があることに気づくし、超越的な場が人間にとって存在せざるを得ないということです。これは当たり前のことですよね。先ほども言いましたが、どんなに大勢の人がいても、顔を見れば、知り合いなのか、自分の親なのかとかは簡単に区別がつく。でも、どこを見て区別しているのか分からない。言葉にはできないわけです。豆柴だって、顔はぜんぜん違う。先ほどのバークの話もそうですが、明示的なものだけを絶対視すると間違うということです。まずは信じなければいけない。そこには理由はない。それが人間という存在なんだということですね。